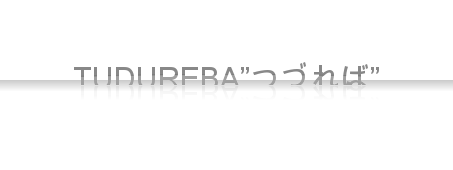このページは、参考書など分厚い本を分冊にする長所と短所および分冊の作り方について記載していくで。
学校のテスト、受験、国家試験、任用資格、英語学習など語学の勉強、独学などなど覚えたいこと、覚えなきゃいけないことが山ほどあるんよね。
「人生、死ぬまで勉強」なんて言葉があるくらい先人の知恵を学べる環境は一種の贅沢かもしれない。
それでも覚えることが多いと参考書や教科書を手に持つだけで「うわぁ、分厚っ!」「開きたくない」と感じることも少なくはないんとちゃうやろうか。
せやから、1つの本を分解して分冊にしてみました。
1つの本を複数に分けるメリット
分けた分だけ軽くなる
キングスライムがスライムに分裂、ポッチャリ魔人ブウが吸収を剥がされて小柄な純粋ブウへ、アンパンマンが優し過ぎてお顔0gになってしまうように当たり前やけど参考書も分冊した分だけ一つあたりが軽くなんねん!
・ストレスも小分けに分割できたらええのにな
持ち運びが便利
一冊を分けた本は軽いということは、部分的に持ち歩くことができるから移動する時も楽チン!
覚えている部分まで持ち歩くことに筋トレ以外の意味はないやろう。
学生時代の通学時に苦しめられる教材という名の鉄アレイ。
「置き勉アカン!」なんて言われようものなら「全校生徒、筋トレ開始」とおっしゃったのかしら?と担任を薄目で眺めた思春期。
*置き晩とは、教科書を学校に置いて登下校すること
置き勉禁止の方針のところでは、宿題がない教科も全て持ち帰らなくてはいけない。
教科書の盗難被害を防ぐ効果はあるが、体が出来上がっていない小柄な小〜中学生にとっては負担が大きいものである。
タブレット教科書などのデジタル機器も持ち歩く時代、子どもに必要以上の通学負担をかけないために荷物の軽量化に力を入れている学校や置き勉ありとする学校も増えてきている。
学校を選べる時代に「置き勉あり」の項目は「制服が可愛い」より優先度が高いだろうか?
Google Teacher 教えてください
G・T・O!
小柄な子がカバンとサブバッグに包まれて「荷物の方がデカくね?ふらついてるけど大丈夫かな」と心配になる場面に出くわしたことはないだろうか?
夢と希望が詰まってたらまだ微笑ましいけれど、教材と着替えが詰まった荷物に押し潰されそうになるなら、逃げたい時に逃げれない規則がポイズンかもしれん。
荷物が多いときの階段の上り下りにはめっちゃ気をつけよう!
人生を踏み外しても即死しないかもしれないが、階段を踏み外したらあり得る。
階段って怖いやん
学校の階段はホラーで怖いけど、その他の階段も現実的に怖いよな。
不安定な一点踵のヒールで階段を歩いてる人って凄い高度な技術よね。
ヒールが折れたら転落するかもしれないリスクと隣り合わせなんやで。
ハイヒールやと爪先立ちしてるようなものやから重心が前に行きやすくて、その状態で急な階段を降ると危ないんよ。
足腰の筋トレをして重心が前に行きすぎないようなヒールの歩き方を体得している方ならまだしも、そんなん学校も親も教えてくれへんやん?
火災や地震や痴漢を考慮するとエレベーターが必ず安全とは言えない一長一短やけど、急いでしまって怪我をしないように移動ルートは選べるなら選ぼう。
階段から落ちても受け止めてくれる白馬の王子様なんているもんじゃないんやから白馬どころか墓場に入りかねない。
地味で汚れた運動靴もいいと思う
すり減っても素敵やん
それだけあなたの体を遠くまで運んだんやで
麦わらの一味でいうところの苦楽を共にしたメリー号のようなものです。
「ありがとう」
また、エスカレーターについても挟まって亡くなる事故が起きてるので気をつけてください。
エスカレーターの非常停止ボタンは、乗るところ、降りるところの内側の下側または手すり付近に付いてるらしいので危ないときは身を守るために迷わず押そう!
停止ボタンの位置はメーカーによって違うから通学や通勤、お買い物の際に「あー、この辺に付いてるんやな」と自分のためにも確認して欲しい。
本当にあったお怪我な話
小学生の頃にランニングマシーンで転倒してベルトに巻き込まれて停止するまで離れられずにベルト状に顔を擦りむいたことがあるんよね。確かに機械の巻き込む力に人間の力で反発するのは困難だった。
現代は、町中に機械物があるので巻き込まれないように逃げやすい荷物の量、巻き込まれない服装を推奨したい。
荷物や服装もさることながら、水分と電解質を補給して熱中症にもお気をつけて!
気温だけじゃなく湿度にも要警戒、いつか湿球温度で天気予報する時代がくるかもせん。
荷物の重さも真夏の湿度も舐める事勿れ
分冊で幅が薄い、開きやすい
分厚い本は、ページを開いた時に重い側に引っ張られて薄い側がパタン!と閉じたりするやん。
あれ、めっちゃ悲しくない?
例えるなら、気になる人に今度一緒に遊びにいこう!って心の扉を開けようとしたら、即答で「むり!」って閉ざされた瞬間の1/100くらいのダメージやん。
100回閉じると1失恋
一冊を分冊にするだけでページ数が減って開きやすくなると拒絶されることなく、いつでもどこでも知識とデートできる!
・傷つくのは、分けるときの側面だけ
得意分野と不得意な分野を分けやすい
参考書なら各科目、教科書であれば各項目に分けることができるので得意分野と不得意分野を分けやすい。
必要な分だけ取り出したり、苦手分野だけ持ち運べて便利!
ぶっちゃけ苦手分野と超苦手分野しかない。得意分野がある人が凄いだけなんとちゃうやろうか。
・飛び抜けてる人ほど幽遊白書のライゼンの仲間たちくらいひっそり暮らしてる説
コピー印刷やスキャンをしやすい
分厚い本は、開くと関節を曲げた時のように中央の割れ目だけ影になるんよね。
ボリュームのあるセンター分けのトランクスくんやドラクエ11の主人公の髪の分け目みたいに。
印刷すると中央が黒くて文字が隠れたり、厚みで湾曲して文字が歪みやすい問題。
それも分冊にして開きやすくなるとスキャンや印刷の仕上がりも綺麗なるので解決します。
・フリマで一冊丸々バラされた漫画を見かけたときは、模写して技術を磨くイラストレーター志望かもしれない
先入観は一種の呪縛に近い
薄くなると威圧感から解放される
目を閉じて想像してみよう。
サバンナに1人きりで置き去りにされて数十匹のハイエナの群れに囲まれた光景を。
あ、終わった
生きて帰れる気がしない
そう、その気持ち。分厚い本を手にした瞬間に心がこう囁く。
やり遂げれる気がしない
分厚い本を分冊にすると、何十匹のハイエナの群れが数匹のチワワになるようなもの。
なんとかなるかもせん
チワワをなめんなよ
知人に自分以外の生き物を倒せるか倒せないかで測る筋肉野郎がいたので昔は隣で戦慄してました「あ、いつかやられるかもせん」と。
それはさておき、分冊すると厚みの威圧感が減ります。
別にやる量が変わったわけじゃないのにコレくらいならやってみようかと踏み出しやすい。
目の前にある情報量が少ない方が負担が少ない。
小さなことを数十回、数百回やると一冊が終わる。自分の手に負える小さいパーツから始めると取っ付きやすいと感じる人には向いています。
人間という生き物は、案外気まぐれでお調子者なんかもせん。
1日1ページであっても年間365ページ進むけれど、現実は復習するので進行速度は半分以下になるやろうか。
復習のタイミングには、よくエビングハウスの忘却曲線が挙げられたりするのでGoogle先生に丸投げします。
・本もプラモデルのようにテーマを決め、見出しを決め、肉付けをする。作り手も時間をかけてパーツごとに作成したはずだ
共同制作かもせん
分冊のデメリット
分冊する手間がかかる
分冊にするには、解体して接着剤やテープで貼り合わせるのでそれなりの時間がかかります。
*分冊のやり方は下に添付
分けただけで勉強した気になる
それなりに時間がかかるので分冊ができた達成感を勉強した達成感と誤認する恐れがある。
参考書を買っただけで勉強した気になってしまうのと現象と同じ。
お化け屋敷のドキドキを恋のドキドキと錯覚する吊り橋効果並みかもしれません。
目を覚ますんだ!まだ、何も始まっていない
恋愛に例えるなら、付き合えたらゴールだと思ってるようなものです。交際したら自分の所有物かのように履き違える過ちがあったり、なかったり。
恋愛には答えがない。たとえ正解らしきものが分かっても環境や性格的に適応できないまである超難関彼氏&超難関彼女。
破局した暁には、こう思われることもあるだろう。
別れた後も恋人面なのマジ勘弁
分冊どころか瞬サツ、デス!
*気をつけてほしい。別れ話が拗れると逆恨みから取り返しのつかないことも生じかねない。
なるべく穏便な別れ方を模索する方が身の安全性は高まるかもしれない。
自然消滅呪文「忙しくて余裕がない」
盗まれたり、紛失する確率が上がる
探し物はなんですか?鞄の中も机の中も探したけれど見つからないんよ!
分冊して数が増えた分だけ、落とし物や盗難など紛失のリスクが上がります。
分冊を失うと再び同じものを手に入れるために原本を買わないといけないから金銭的なリスク分散にならんのよね。
せいぜい、飲み物こぼしたときのシワやシミの被害が分冊だけで済むくらい。
・学生時代に盗まれたもの→シャーペン、教科書、お弁当の具材、飲み物、財布、靴、部活のラケット、ハート
人間不信確定
どうやら一通りパクられるほどには治安が悪いのかもしれん。
海外みたいに命や腕ごと持っていかれないだけ平和とも言えるやろうか。
高価なものは学校や職場に持っていかず、
文房具は100均で揃えることを推したい
ペンだけは、書きにくかったらモチベーションが下がるので書きやすくて指先が疲労しにくいものを使用してもいいかもしれません。
・高価な物を身に纏うことを全裸で蜂蜜を塗って熊の前に立つことと大差ない行為やと思ってます
プーさんみたいに優しくない
三次元の現実熊は、狩猟によって警戒心が強まった熊の世代からそうではない世代になってきたとかで熊による被害も増えているので注意したい。
熊が近づいてきているときに興味本位で自分から窓や扉を絶対に開いてはいけません。
余裕があるなら屋外用の監視カメラを取り付けた方がいいです。特に一軒家や駐車場で塀の当て逃げや車へのイタズラとかもあるので。
被害があったら警察を通した方が賢明です。対人の場合も個人間でやると暴力を振るわれることもあるかもしれないので気をつけてください。
何の本か分かりにくくなる
分冊すると表紙がなくなり、ぱっと見ただけでは何の本か分かりにくくなります。
表紙を自作したり、100均などのラベルシールを貼ると解決します。
・表札がない家やマンションの号室宛の荷物に配達員が困るみたいな感じ
配達員に感謝しかない
分冊にして授業でページを飛ばされると困る
普段の授業で使う本を分冊するメリットは、荷物が軽くなるくらいしかありません。
忘れ物が増えるかもしれないし、授業のときに何を血迷ったのか数十ページ先を開いて!と飛ばす教師もいる。
必要なことを教えてくれているのだが、分冊した身としては「あ、圏外」です。
分冊した自己責任
・教えてくれる人が、どのページに移動するか予測できないので誰かに教わってる最中の本については分冊にしない方がええよね
シワや折れ目が付きやすい
原本の分厚さがあると外部からの衝撃に対してある程度の耐久性があるけれど、分冊にして薄くなると耐久性が落ちて痛みやすくなるんよね。
分冊した本は、鞄の収納スペースを分けたりして労ってください。
・プラモデルやミニ四駆を肉抜きして軽量化すると、落としたり衝突したときにバキバキになりやすいみたいなね
罪悪感を伴う
「折角、製品化された書物をバラすなんて恐れ多いことを」となんとも言えない罪悪感に包まれることがあります。
罪悪感は最初だけ
クソみたいなセリフやけど、分冊にする行為は犯罪ではないため良心の呵責に苛まれる必要はない。
不必要に切り刻むわけでもないし、より情報に対して向き合うための行為を恥じることなかれ。
使われず綺麗なままの本、使い古されてボロボロな本、作者はどちらに作って良かったと感じるだろうか。
・別に作者のために学んでないんだけどとは言わず、作ってくれてありがとうの気持ちで書物に向き合いたい
度が過ぎると罪悪感は最後まで続きます
ほな、参考書や教科書を小冊子風にしていこか
分冊にするために必要なもの
分冊工程①範囲ごとに切り分ける

カッターやデザインナイフを使って、分冊したい章や節など必要な範囲に区切りながら切り分けます。
切り分ける時に縁が硬い場合は、熱で接着剤を溶かしたり、湿らせて縁を剥がしてから切りましょう。
しっかり本を開いてから刃をいれないと裁断面が歪みやすいので、本を目一杯に開いてから反対側に折り曲げるくらいのつもりでメキメキ、メキメキ、メキシコ〜♪
は?
刃!正解!
怪我しないように気をつけながらカッターを扱ってね。
切れ味重視なら、オルファのデザインカッターがおすすめやけど本が分厚過ぎると刃が反対まで届きにくいこともあるので厚みで使い分けが必要かもしれません。
②切り出したページの束の背(縁)を接着剤で補強する

切り出した部分の背(縁)は、歪に切れたり破れたりしやすいので木工用ボンドなどで縁を補強します。
ページの束がバラけてしまわないように満遍なく塗りつけて乾くのを待たなあかんやけど、待つ間に他の項目を切り出しちゃってください。
乾燥を早めたい場合はドライヤーを遠目から当ててもええかもせん。
ドライヤーを近づけ過ぎると紙が燃えるので厳禁!
ドライヤーからファイヤーになったら洒落にならんでな
③切り出した最初と最後のページを保護する

切り出した部分の最初のページと最後のページに印刷用紙や厚紙などを本の大きさに合わせて貼り付けた方が仕上がりが美しい。
美しいのは最初だけ
これから使い倒して汚れるのだから、美しさにこだわらなくてもいいです。
先に用意しておいて、②の時に一緒に接着剤で貼り付けると二度手間にならない。
※この段階で厚紙と「製本テープ」で分冊した縁を補強して完成でもOK!その方が簡単です
黒い厚紙に黒い製本テープを使用すると、見た目はデスノート、中身は分冊、その名も「黒表紙の分冊」が出来上がります。
分冊を使った人間は、筆記試験や面接に受かってやると思え!天国や地獄には行けるかもしれない
④厚紙や紙袋でカバーを作る(撥水性加工だと汚れにくい)

厚紙や紙袋を分冊した本より横幅を長く切って縁の部分に両面テープを貼ります。
*ブックカバーみたいにしたいときは、折り返す部分が必要やから折りしろ必須
カバーを固定したい場合は、先に折り目をつけてからカバーの両端に両面テープや糊を使用します。
*折り目をつける前に先にテープを貼り合わせてしまうと開きにくくなるので要注意!
*画像では、水を弾きやすい(撥水性のある)紙袋を解体してカバーとして使用してます
最初ページや最後のページがむき出しやと汚れや擦れて破れるリスクがあったり、折り畳み傘やペットボトルと一緒に鞄に入れているとふやけてインク落ちするリスクがあるから表紙やカバーの素材はお好みで!
⑤貼り付けて完成

*貼るときは、閉じたまま貼りましょう
カバーの折り目を本が開いた状態で貼り付けてしまうとその分、閉じた時に短くなってしまうので上手く閉まらなくなります。
持ち運ばないんやったら分冊に切り離して製本テープで側面の止めるだけの方が作業時間は大幅に削減できます。用途に合わせて自分好みに染め上げたってください。
後は、自分が分かりやすいように科目や項目のラベルシールを貼り付けて完成です!

さぁ、行くんだ、その表紙を開けて新しい本に知識を貰おう。
効率を求め過ぎると非効率になる逆転現象にハマりやすい現実。まるでレベルが上がるまで装備できないRPGの装備みたいだ。
これらの脱線しがちな語彙力を見てお分かりの通り、どうか私のようなおバカにならないで欲しい。参考どころか悪い見本である。